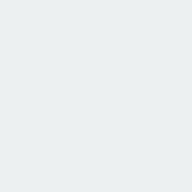東洋と一口に言っても実に様々で、メソポタミアの影響を直接被っているインドだけでも、「仏教占星術」と「シッダーンダ」系の占星術との二つに大きく分けることが可能だったりします。
ただ、そんな東洋占星術ですが、天宮を獣帯で一二宮に分割してそれぞれの性質を特定する点では、西洋占星術と同傾向にあります。大きな違いは、この一二宮を更に細分化して三六宮(=デカン)を制定した点ぐらいでしょう。
インドでは紀元前1500年ごろから既に12ヶ月・1年360日と定めた暦が採用され、5年ごとに閏年を加えて歳差を調整するほどに天文学が発達していました。
ここにメソポタミアの占星術書「エヌマ・アヌ・エンリル」が伝播して仏典にも取り入れられています。これらを踏まえて更にインド固有の占星術としてひとつの完成を見たのが5世紀に編まれた「暦法大全=ブラハット・サンヒター」で、これを仏教に取り入れたのが「宿曜経」以後の密教仏典になります。
一方、中国でも周の時代には現行の陰陽道で知られる二八宿が制定されていました。これは無論大河の治水と農耕に関る暦法の制定に繋がっておりまして、中国の宿の概念は月の運行に端を発しています。
この周代の暦にインド伝来の「宿曜経」を加えたのが四象八卦から展開される星宿図だったりします。また北極星を中心にする北斗七星も重用されて、後に独自の占星術を成すに至ります。
東洋占星術の源泉はインド天文学とメソポタミアからきた占星術ですが、独特の解釈が存在しています。
最も著名な占星仏典は「宿曜経」ですが、唐代の僧・不空三蔵によってインドから持ち帰られたのが端緒でした。これが密教で独自に発展したのが「九曜」で、七曜に二星を加えた、西洋には見られない固有の占星術です。
ラゴウ、計都が月日の七曜に加えられて九曜を形成する訳ですが、この二星は特殊な、一種観念的な存在です。
ラゴウ星は太陽や月を食べる=皆既食を誘発する暗黒の星とされ、西洋占星術で言うところの、降交点=ドラゴン・テイルに相当し、一方の計都星は周期的に天体を過ぎる箒星がその正体であるとされています。
またラゴウは黄幡神とも呼ばれますが、これは皆既日食の時に観察されるコロナが黄色く輝く様子を形容していると言い、計都の別名・豹尾神も静養占星術で言うところの昇交点=ドラゴン・ヘッドでの皆既日食の形容であるとされています。
いずれの星も大凶の卦といわれています。